新しい物理の誕生を告げるμ→eγ崩壊発見にスイスで挑む
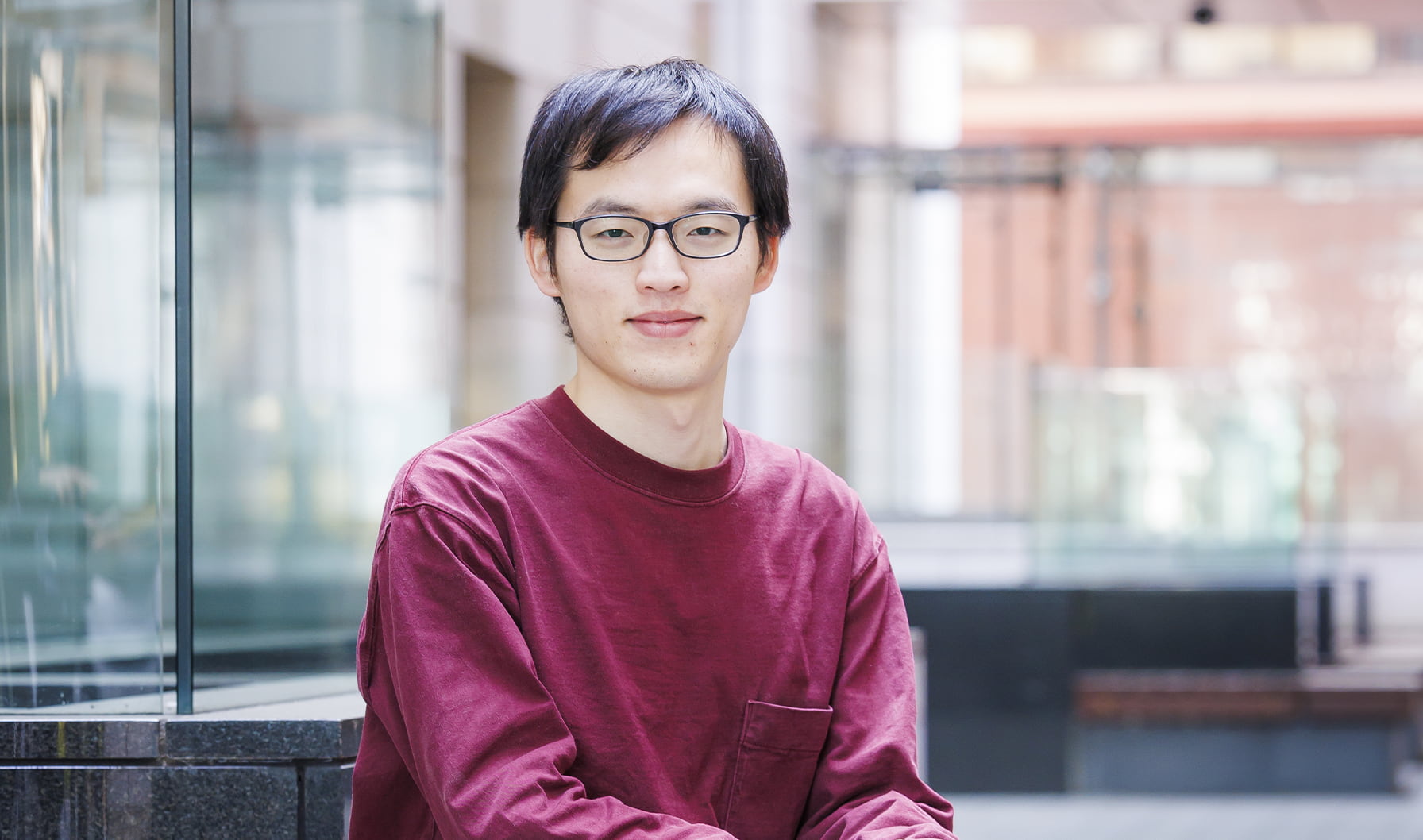
どのような研究に取り組んでいますか?
2023年の修士1年の秋から、スイスにあるポールシェラー研究所(PSI)でMEGⅡ実験に携わっています。修士1年の時は120日間、2年の昨年は241日間、つごう1年もスイスにいました。今では日本よりスイスの方が馴染み深いかもしれません。ICEPPの説明会でスイスに行くのは聞いていましたが、まさかこれほど長くいることになるとは想像していませんでした。修士1年前期で修了要件の授業を全部取りきったら、その後気兼ねなく行けると聞いていたので、とにかく頑張って、念願のスイスに飛び立ちました。
とはいえ、実際にスイスに行ってみると、英語は向こうの人のほうが断然うまくて驚きました。そもそも研究所があるのはドイツ語圏の地方でしたので、最初のころは現地の人とまったく会話ができませんでした。PSIでの研究も想像以上に大変でした。私は学部生時代に理論を卒業研究でやっていたので、実験で手を動かす経験がありませんでした。ほんとうに何もわからないゼロからの出発でした。

MEGⅡ実験について詳しく教えてください。
MEGⅡ実験というのは、μ(ミュー)粒子がγ(ガンマ)線を放出して電子に変わるμ→eγ崩壊を探索するプロジェクトです。このμ→eγ崩壊が発見されれば、現代の素粒子論の標準模型を超える「新物理」が見えてくるという重要なものです。この実験では、γ線を測定するために液体キセノンを用います。γ線が液体キセノンの中に入ると、キセノンの原子を励起させてシンチレーション光というかすかな光を出します。その発光の位置、時間およびエネルギーを測定するのが液体キセノン検出器で、この検出器に関連することが私の研究テーマです。
PSIでは、この検出器の運用自体も私の大きな任務の一つで、2024年には貴重な液体キセノンが検出器から漏れて失われるという問題の解決にもあたりました。二つの原因を特定して、バルブに起因した大きな漏出のほうは解決できましたが、キセノンが入った容器から外に染み出ていく漏出のほうは今も続いていて、これはこれからスイスに戻ってきっちり直す予定です。
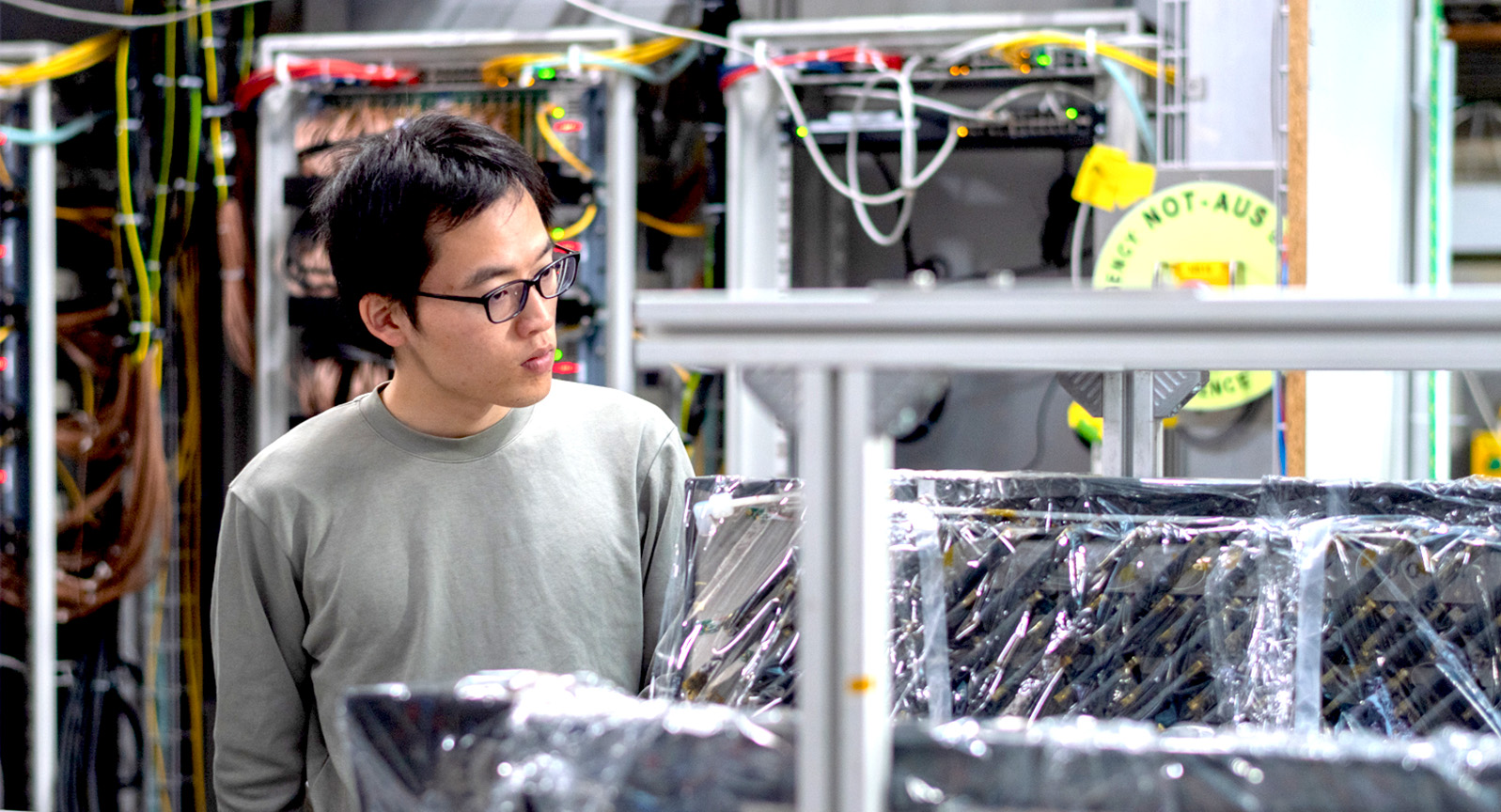
問題解決の見通しは立っていますか?
液体キセノン検出器では、紫外線よりさらに波長が短いシンチレーション光を検出できるように、特殊な加工を施したVUV-MPPCと呼ばれる半導体光センサー(SiPM)が使われています。このVUV-MPPCの光子検出効率(PDE)がMEG II実験中に下がっていますが、まだ原因はわかっていません。一種の放射線損傷だと考えられますが、そのメカニズムは謎のままです。私はこのVUV-MPPCの放射線損傷の原因解明に向けて、PSIでラボ実験を行いました。その結果、実機のVUV-MPPCで見られるPDE減少再現の可能性を示すことができました。今後、さらに測定の精度を上げた実験を行い、PDE減少再現を目指していくことが、私の今の目標です。
また、液体キセノン検出器の最大の謎として、エネルギー分解能の悪化というのがあります。これは分解能の実測値がシミュレーションから得られた値より2倍悪いというもので、これが感度を大きく制限しています。エネルギー分解能の改善が強く期待されており、仮に改善が見込めない場合でも分解能悪化の原因を特定しなければなりません。液体キセノン検出器は900Lの液体キセノン、それを取り囲む4,760個のVUV-MPPC・光電子増倍管で構成されています。分解能悪化の原因が液体キセノンの性質にあるのか、それとも光センサーにあるのかを区別し、明らかにするのはMEG II実験だけでなく、関連するその他の実験でも重要となってきます。VUV-MPPCのPDE減少の原因解明の研究は光センサーの特性を理解するという観点から、まさに分解能悪化の原因解明に直結しています。私は研究活動において、小さな疑問に一つ一つ丁寧に向き合っていくことで大きな問題を解決することができると考えています。

PSIでMEGⅡ実験に携わっている間にμ→eγ崩壊が発見されたどうですか?
それはノーベル賞級の研究に自分が少しでも役に立ったということになるので、ものすごいロマンを感じます。それに、MEGⅡ実験を提案したのが私たちの研究室のボスの森俊則先生ですし、長年にわたっての東大とICEPPの貢献度はものすごく大きいと思うので、そういう意味でのロマンもあります。海外の一流の研究者たちと切磋琢磨しながら実験に取り組めるのは研究冥利に尽きますし、異文化を見聞きしたり周りのひとと交流する楽しさを、言葉では言い表せないくらい実感しています。